- TOP
- COFFEE BREAK
- エッセイ*名越康文【 「苦味」 という嗜好。】
- エッセイ*名越康文【 「苦味」…
COFFEE BREAK
文化-Culture-
エッセイ*名越康文【 「苦味」 という嗜好。】

珈琲は私にとっては必需品だった。必需品という言葉をあえて使うのは他でもない、40代まではまるで気付薬がわりだったことを告白しなければならないからだ。学生時代は昼は空手の稽古、それが終わると千日前に直行してジャズ仲間とセッションとおしゃべり、つまり夜遊びに明け暮れていたから朝は眠くて仕方がない。医者になってからは当直や救急業務でやはりとにかく眠い。身体に染み渡るブラックコーヒーの刺激を求めて1日に3杯は飲んでいた。ところが30代後半から春先2月くらいに必ず禁糖をやるようになった。禁糖とは夏に向けて身体を整えるために約1週間だけ、甘いもの(砂糖)、酒、珈琲を控える野口整体(整体の源流といわれる野口晴哉が創始した健康体系。禁糖は現在の整体協会の総帥・野口裕之氏が提唱)の技法である。この禁糖明けの1杯の珈琲が格別なのだ。五感で旨さを実感するという感じだ。この経験は私にとっては大きかった。珈琲だけではなくお茶やお酒も、立ち止まって味わうということを覚えたからだ。
現在は大体1日1、2杯、味わって飲む。午前中はカフェオレやカプチーノを飲むこともある。地方出張が2週おきにあるので、ホテルで朝食というパターンも多いのだが、その時だけは朝食ビュッフェで冷たい牛乳をたっぷり入れてぬるくしたミルクコーヒーをゴクッとやる。喉越しがよくて最高なのだ。
しかし最近になって、自分にとっては心を溌剌とさせる作用は珈琲のカフェインだけではなくて、むしろ淹れたての香りの方だということに気づき出した。これは自分にとっては驚きだった。何せ医者の端くれである。人を覚醒させるのはカフェインの作用だと信じて疑っていなかった。しかし実際には芳しい珈琲の香りが、どれだけ心身の活性化に役立っていることか。香りという〝体験〟はほんの一瞬の出来事であるから、感性が成長しないうちは見極められなかったのだろう。しかし香りという数秒にも満たない経験に、私の心身は大きな影響を受けていることは間違いない。一瞬で溌剌とした気持ちになる。ある研究によると珈琲の香り成分は800種類以上もあり、主たるフレーバー成分だけでも数十種類もあるそうだ。それらの成分が人間の心身や細胞にどのような影響を与えるのかについては、大半が未知の分野なのではないだろうか。
東京にいる時は、おいしい珈琲屋が数軒あって嬉しい限りだ。その中でも駅前の店のマスターとはもう顔馴染みで、私が珈琲好きと知っていろいろと教えてくださる。私は一向に体系立ったことは覚えられないのだが、そのマスターに、これはブラックでとか、これはミルクと砂糖を多めで、とか言われてその通りに飲むと、てきめんに旨いので毎回嬉しい経験を積むことになる。向上心はないが、旨さの経験は確実に積み重なってゆくので、ますます珈琲愛が深まるといった良い循環で歳を重ねていられると思い、感謝している。
珈琲は酒タバコなどとは違い、法律規制はないものの、いわば第3の嗜好品であると常々思っている。では嗜好品とは何か。それは大人の嗜みという意味である。大人の定義はさまざまで、年齢以外に明らかな基準はない。しかしながら心理学的に考えてみれば、たとえば人生の諸問題に対して、過去の経験に照らし合わせて客観的な距離で対処できる人、ということになるのだろうか。意味はわかるが我ながら無味乾燥な言葉である。これよりは味覚からみた大人の定義の方が、私的にはよほど簡潔である。つまりは苦味を好むようになるということである。子どもは苦味を好まない。子どもが先ず好むのは甘みである。甘みだけを追いかける時期が過ぎると、塩味、ついで辛みだろう。これは刺激を求めるわけで、こじつけていうのならばスリルを楽しみたくなる少年期・思春期と符合する。そして大人になってからようやく嗜好するのが苦味である。つまり苦味こそ嗜好品の必要条件と言える。実は味にはその奥に渋味というものが多分あるのだが、よほど疲れた時でなければまだ私にはきちんと味わえない。
考えてみると人間の欲望の深さを示すものとして、食文化ほどわかり易いものはないのではないか。食べ易く、安全で消化を助けるために工夫されたと思われる調理法は、おそらく気候の激変が緩和された13000年ほど前から、人間の味覚(この中には視覚、聴覚、嗅覚などの感覚も含まれる)の探究へと、つまり文化へと発展していったのではないか。発展というと整然とした道筋のようだが、そうではない。無限のバリエーションと逸脱がその長い食文化の栄枯盛衰には含まれている。その中でいつしか人間は、動物では同化が難しい味まで楽しめるようになったのである。
苦味とは人生の失敗、後悔の味、つまり苦い味とは異なるように思う。苦味を嗜好する人とは、人生が限りある年月に過ぎず、その有限の時間は正に砂時計の砂のように一刻一刻を刻みながら滑り落ちてゆく、ということを愛着と諦観をもって味わえる人のことである。その証明が苦さへの嗜好である。珈琲は食文化という巨大な帆柱を支えるロープの一つを、しっかりと結わえ付けている。
1960年奈良県生まれ。精神科医。相愛大学、高野山大学客員教授。専門は思春期精神医学、精神療法。近畿大学医学部卒業。臨床に携わる一方で、コメンテーター、映画評論、漫画分析など様々な分野で活躍中。


 健康
健康 美容
美容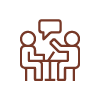 インタビュー
インタビュー 文化
文化 世界のコーヒー
世界のコーヒー 基礎知識
基礎知識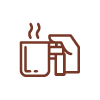 楽しみ方
楽しみ方