コーヒーの未来を救うアグロフォレストリー

世界中で愛され続け、私たちの日常にそっと寄り添うコーヒー。普段の生活で何気なく手にしている一杯の裏側には、環境問題や生産者の貧困といった課題があることをご存知でしょうか。消費量が世界的に拡大している一方で、気候変動などの影響や生産者の離農により生産量の減少が危惧されているいま、私たちにできることはこうした課題に目を向けること。そのはじめの一歩として、今回はSDGSの観点から注目されている農法「アグロフォレストリー」について解説します。
Profile
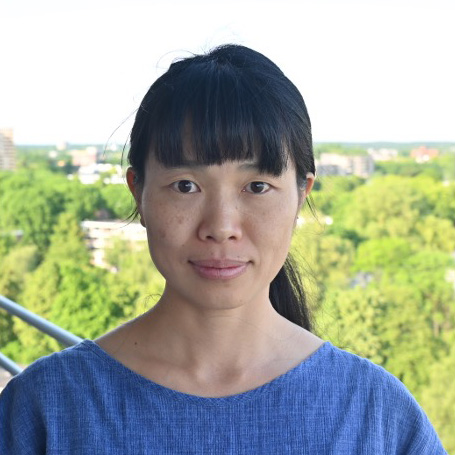
教えてくれたのは…… 藤澤 奈都穂先生
筑波大学人文社会系 助教。主な研究対象は、ラテンアメリカ地域で実践されている農業生態。なかでも地域で伝統的に実践されてきたコーヒー・アグロフォレストリーに着目し、小規模農家や地域住民の生活を軸に、森林の保全というグローバルな課題にアプローチすることを目指している。
Contents
コーヒーが飲めなくなる…?

コーヒーが抱える課題のひとつに、まずは環境問題が挙げられます。極端な寒さや暑さに弱く、適度な雨量を必要とするコーヒーは、主に赤道周辺の熱帯地域や亜熱帯地域で栽培・生産されていますが、同時に大規模な農地を確保するために多くの樹木が伐採され、熱帯林が失われつつあります。これはコーヒー栽培に限った話ではありませんが、多様な生き物のすみかであり、また(温室効果ガスである)二酸化炭素を吸収する働きがある熱帯林が減少すると、地球温暖化が加速し、生態系にも大きな影響を与えます。これは、コーヒーの栽培適地の減少にもつながります。
また、コーヒー生産者の貧困問題も長年の課題となっています。コーヒーの約9割が小規模農家によって生産されており、その多くが発展途上国の農家と言われています。こうしたなかで、経済的な対応力が低い小規模農家は近年のコーヒー価格の乱高下により大きな影響を受けており、持続的な生産を実現するためには安定した市場の形成が必要不可欠とされています。
藤澤先生
実はコーヒー生産者に届くお金はすごく少ないというのが現状で、生産者が十分な利益を得られないというのは長く続いてきた課題としてあります。その結果、生産者が農業を辞めざるを得ず、コーヒー生産自体が衰退していき、いつかコーヒーが飲めなくなってしまう。これは、今後も持続的に消費を続けていくことができるのかという消費者側の課題につながっていく問題でもあります。
アグロフォレストリーとは

環境問題や生産者の貧困といった課題を抱えるなかで、持続可能なコーヒーの未来を実現するため従来のプランテーションに変わって推奨されているのが、樹木とともに農作物を育てる「アグロフォレストリー」です。
アグロフォレストリーとは「樹木とともにある農業」のことで、これをもともと日陰の下で生育するのが適しているコーヒー栽培に置き換えると、日陰を作る高い木・シェードツリーの下で、農作物であるコーヒーノキを育てるということになります。シェードツリーの種類は地域によって様々ですが、主に肥料となるマメ科の樹木や、バナナなどの果物や木材になる樹木などが植えられます。つまり、農作物に加え、有用な樹木を組み合わせられるというのがアグロフォレストリー。地域にもともと生育している樹木をシェードツリーとして利用すれば、森林保全にもつながります。
また小規模農家の貧困問題においてもメリットがあります。日陰の下で育てる農作物の他に、シェードツリーになる作物を育てることで多様な収穫物を得ることができるため、コーヒーの不作の影響を緩和し、安定した収入源につながります。さらには、“土地に木を残す” というアグロフォレストリーの仕組みは、資源の銀行として役立ちます。例えば、農村を出て働きに行った場合でも、コーヒーと有用な樹木を植えた土地を残しておけば、仕事を失い戻ってきた時や急な出費が必要なときに、コーヒーや木材を売って収入としたり、自給用の作物を確保することにつながります。
藤澤先生
とりわけ小規模なコーヒー農家にとって、アグロフォレストリーはかなり重要な役割を果たしていると思います。肥料や農薬を撒かなければならない単一栽培とは異なり、アグロフォレストリーは組み合わせたシェードツリーが土壌の質を高めてくれるため、農家の投資費用を抑えることができるほか、花粉を媒介する蜂やその他の昆虫の生息地にもなるため生産性の向上にもつながります。さらには適度に樹木があることで、もともと森林に自生していたコーヒーの生育環境が整い、自然の力を利用した長期的な生産を可能にします。
このように多くのメリットがありますが、いずれにしても押さえておきたいことは、アグロフォレストリーは最近になって作られた新技術ではないということ。アグロフォレストリーはもともと、世界中のさまざまな地域の小規模農家によって在来の農業のなかで実践されてきており、それが今、いろいろな農地に広く応用されています。
持続可能なコーヒー生産を実現するために

消費国である日本にとって、あまり聞きなれないアグロフォレストリー。今後、私たちがコーヒーの課題をより身近に感じ持続可能な将来を実現するためには、まずは現地の状況を知るということに尽きるのかもしれません。
藤澤先生
こうしたコーヒーの課題を消費国である日本全体が身近な問題として捉えるためには、まずは味だけではなく、生産段階の環境配慮や社会貢献といった部分もコーヒーの付加価値として存在するということを企業が発信し、広く認識してもらうことが求められると思います。それは、(フェアトレードなどの?)認証マークだけを見ればいいと言うことではありません。すでに多くの企業が実践していますが、特定の産地との関係性を築き、そこで得た情報を消費者に伝え、消費国が現地の具体的な情報を知るという取り組みは非常に重要です。またアグロフォレストリーにおいては、近年新たに誕生した技術なのではなく伝統的な知識に基づいたものであり、そこには文化的な背景も存在するということが世界で広く評価されることが必要です。これは生産地の生産性を上げて、それを高く買い上げればよいという話ではありません。文化社会的な農村の価値を高めるようなコーヒーの市場が求められており、それが持続的な生産につながるのです。
アグロフォレストリーは、コーヒー以外の作物での実践も可能です。また、コーヒー栽培地以外の場所でも導入することができます。通常、森と農地は別の土地利用とされ、管理主体や目的が異なりますが、アグロフォレストリーのような連続した利用があるということを再認識することは、分断しがちな森と農と暮らしの関係をつなぎ合わせる役割を果たすのではないでしょうか。
